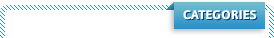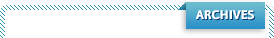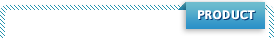北村 圭介
株式会社キタムラジャパン
代表取締役
大正12年創業の枕専門メーカー「枕のキタムラ」4代目。曾祖父から伝わる経験やノウハウを活かし、眠りに対するキタムラのエスプリを枕にしています。枕屋4代目のブログ「まくろぐ」では、枕のことがメインですが、睡眠やモノづくり、マーケティングなど独自の想うことを書きます。
北村 圭介
株式会社キタムラジャパン
代表取締役
大正12年創業の枕専門メーカー「枕のキタムラ」4代目。曾祖父から伝わる経験やノウハウを活かし、眠りに対するキタムラのエスプリを枕にしています。枕屋4代目のブログ「まくろぐ」では、枕のことがメインですが、睡眠やモノづくり、マーケティングなど独自の想うことを書きます。